入社からの流れ
flow

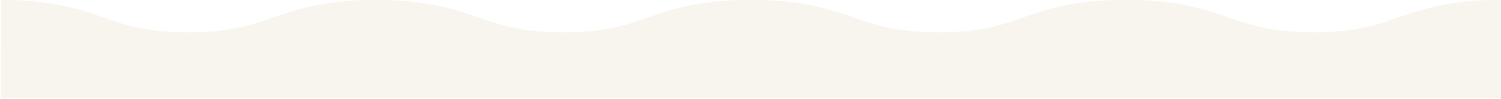
新卒入社後の研修内容
社会に出てからがスタートです。あなたのやる気を本気でサポートします!
“一人前のお金の専門家へ”
井上会計事務所では、学習意欲満開だけれども、学習環境にはあまり恵まれていない方を特に歓迎します。
本当は大学に進学して勉強したかった・・・けれど、諸事情でそれはあきらめることにした。
敢えて就職して会計の仕事を覚えたいと思っている。
そんな方が一番伸びる可能性ありです。
-
- 01総務担当入社直後 1ヵ月
- 電話応対、来所者応対を中心に総務の仕事から始めていただきます。
-
- 02簿記復習 3~2級入社直後 1ヵ月
- 個人のレベルに応じ、入社直前にカリキュラムを組みます。日商簿記の取得がまだな場合には、受験を最優先にします。
学習は業務として行うため、指示された業務がない時間はすべて研修に充てていただきます。
-
- 03所得税法研修入社~3ヵ月後
- 簿記の復習が終わった段階で、所得税法の講義をWebで受けていただきます。教材は事務所支給、大原簿記の教材を使用します。
-
- 04申告実務応援入社~3ヵ月後
-
帳票類の整理、電子申告の設定他指導
毎月その月にやるべき業務を整理し、監査担当者の雑務の補助を少しずつ始めます。
-
- 05消費税法研修入社後 5か月~11月
- 所得税の研修が終わった段階で消費税の教材を進めます。個人の様子を見ながら進行速度を決定します。
-
- 06年末調整実務 研修入社後 12月~1月
- 所得税テキストより、年末調整について抜粋して再度研修を行います。所長税理士より直接本人の理解度を確認しながら確実に作業が出来るように研修を行います。理解度に応じて作業を割り振り、年末調整の補助の実務に入っていきます。
-
- 07確定申告実務 研修1~3月
-
所得税テキストを参照しながら、実務に入ります。
所得控除の内容チェック、申告書チェック、
領収書貼り付け、控え書類作成、
電子申告サポート他
監査担当者の業務をサポートする形で実務に入ります。この時期は残業が発生します。
-
- 入社2年目4ヵ月~
-
一通り申告実務を経験した段階だと思われます。ここから、簡単な入力作業を担当していただきます。
税法の研修は、所得税、消費税の学習が終わっていれば法人税を始めます。新しく、新卒者が入社してくる時期でもあります。新卒者を先輩としてフォローしつつ、それまで行っていた来客応対などの総務の業務を交代します。先輩所員とも業務の調整を行い、担当業務を決めていきます。
担当関与先を持つのはもう少し先になる見込みですが、作業自体の負荷を上げていく段階です。法人税の研修を終えるタイミングで担当先の割り振りが発生する可能性があります。
-
- 入社3年目4月~
-
遅くともこの段階で、法人担当先の割り振りを行います。月次関与の個人と法人合わせて15~20件くらいの担当先を持つことを目標にしてもらいます。
まだ単独では法人税の申告を行うことは難しい段階だと思われますので、先輩所員のフォローを受けながら担当先を増やしていきます。
新しく新卒が入社してくるタイミングでは、後輩の指導も一部担当していただきます。勉強のやり方や質問などにも対応していただくことになります。 教えることが一番の勉強になる、そんな時期だと思いますので、後輩への指導を積極的に促していきます。
-
- 入社4年目4月~
-
単独で担当先を持てるようになる時期と思われます。完全に独り立ちし、フォローされるよりもフォローする側に回っているはずです。
このタイミングで、面談を通じ、本人と給与体系について5か年計画を組みます。 昇給の時期やタイミングを、担当する業務の深さや量を斟酌して決定します。もちろん、本人の実力に応じ、オーバーワークや過少負荷にならないように調整をしていく前提で行います。
通常、ここまで順調にきてようやく0.8人前くらいだと思われますので、昇給についてはまだ土俵に乗りませんがここから多少上げていく可能性が高いです。本人の実力と希望次第です。 この4年目を乗り切った段階で、本当の意味で一人前と呼べる状態になると思われます。
-
- 入社5年目4月~
-
4年目最初に決めた5か年計画の2年目に該当します。計画に従って業務を行います。
計画次第では、相続税法の分野へジョブローテーションする可能性もあります。この辺りは本人の希望と事務所のその時の状況で決定されます。 5年目以降は、本人の実力次第で役職が付いてくる可能性があります。
税理士試験の受験について
5年目以降、税理士試験の受験希望者には、学校通学費用もしくは教材支給及び試験休暇を取得する権利を付与します。
特別待遇になるため、給与体系、試験勉強の進め方、スケジュール管理、担当先の負荷軽減他取り決めが必要になります。
また、希望者全員に与えるものではなく、それまでの仕事ぶりや本人の資質、将来性を鑑みて所長税理士と面談を重ねたのち、該当者を選抜します。
とはいえ、若い年齢から難関試験を受験することは大変意義があり、喜ばしいことではありますので出来るだけ応援する方向で選考をする所存です。
