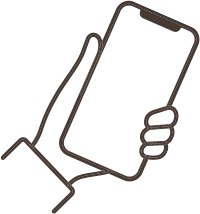よくあるご質問
Q&A

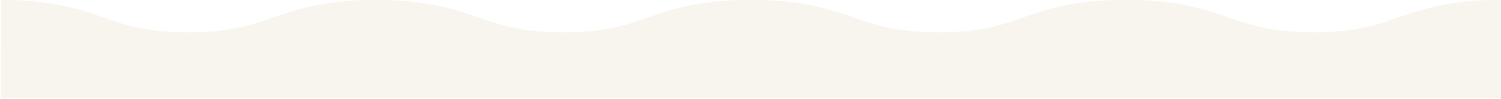
- ホーム
- よくあるご質問
相続税の相談を承る場合によくいただく質問をまとめております。
-
うちの場合相続税はいくら?
-
被相続人の全ての財産の相続税評価額と法定相続人の人数、更に「誰がどの財産を取得する」
遺産分割方法によって相続税額が算出されるため、一概には言えません。
被相続人の財産資料を全てご提出いただき、その資料を元に調査を進め財産の総額が算出されます。
その後相続人様同士で遺産分割協議をしていただき、その分割方法が決まってからようやく正しい相続税額が計算されます。
-
遺産分割の割合 法定相続分で分けないといけないんでしょ?
-
いいえ違います。
遺言書がない場合には、相続人全員で話し合って合意すれば必ずしも法定相続分通りに遺産を分ける必要はありません。
-
遺産を受け取らない場合は相続放棄の手続きが必要?
-
「相続放棄」とは、家庭裁判所で行う、非常に強力な法的手続きです。
一度受理されると原則として撤回はできません。相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになります。これは、不動産や預貯金などプラスの財産を相続する権利と マイナス財産を引き継ぐ義務、遺留分など相続人として主張できる全ての権利を全て失うことを意味します。
また、繰り上がりで思いも寄らない親類が相続人になってしまう場合もあり、注意が必要です。
安易に相続放棄を選択せず、専門家に相談しながら判断することが重要です。
一方、財産放棄という意味合いで、相続人全員の協議により合意した「相続財産を受け取らない」旨の遺産分割協議書を作成し相続手続きを進めていく方法が後のトラブルもなく一般的です。
-
相続財産の範囲の勘違い(亡くなる前に解約すれば相続財産にならない)
-
相続発生日前に預金解約し、現金で保管していた場合や、他の家族の名義に変更していた場合も、被相続人の財産として計上します。
また預金を他の家族の名義に移し、その名義の方が自分のために使ってしまっている場合は被相続人からの贈与を受けた事となり、贈与を受けた方の贈与税申告が必要となります。
-
預金調査の意味(なぜ5年分も調べるの?)
-
税務署は全国の金融機関から被相続人と配偶者・子・孫・子の配偶者などの「預貯金残高」や「入金・出金の取引履歴」、証券情報を入手する権限を有しています。
また、相続税・贈与税の税務調査で最も指摘を受けるのが、現金・預貯金の申告漏れという情報も有ります。その金額が多額であれば税務調査につながる可能性が高まります。銀行口座の不明出金があれば、税務署は解明するまで納得してくれないでしょう。
税務調査による追徴課税には、本税のほか加算税と延滞税・重加算税(意図的に隠したり、過少に申告した場合)があり、思いのほか多額にのぼる例もあります。
このような状況を避けるために、ご依頼の際にはあらかじめ全ての情報を提示していただき、相続人の皆様と一緒にお金の流れを確認し、相続財産として計上が必要なものを漏らさず申告します。それが結果として税務調査を防ぐことにつながります。
-
生前贈与・持ち戻し分(これも財産に入るの?)
-
被相続人から相続開始前の一定期間内に、暦年課税制度による生前贈与を受けていた場合、この生前贈与財産を相続財産に加算(持ち戻し)して、相続税を課税するルールとなっています。
令和5年12月31日迄に贈与された財産については、加算期間3年ですが、令和6年1月1日以降に贈与された財産については、加算期間7年となります。
-
名義預金・名義保険について
-
子どもや孫、配偶者など、家族の名義で開設した預金口座(保険契約)に自分(被相続人)のお金を預ける行為をいいます。
例えば父が子供名義の口座にお金を預けていた場合では口座の名義は子供ですが実態として父が自分の財産を預けていたことになりますので、被相続人御本人の財産として相続財産に計上されます。
-
価値のない土地(畑・田んぼ・雑種地)どうして評価額がつくの?
-
土地の評価につきましては、国税庁の財産評価基準書をもとに評価額を算出しています。
田・畑につきましては、倍率表にて、〇〇市の〇〇町の市街化区域又は市街化調整区域により倍率というものが定められています。
市役所の固定資産税評価額にその指定された倍率を乗じて評価額を算出する場合や、市比準(宅地評価をもとに算出する方法)で評価額を算出する場合等地域や地目により評価方法を指定されています。これにより皆様が思っている以上に高額な価額になってしまう場合もあります。
-
どうして、10ヶ月もかかってしまうの?
-
被相続人が亡くなった相続発生日を基準日として10ヶ月後の応当日が相続税申告と納税の期限日となっております。
被相続人の戸籍収集からはじめ、土地・家屋等の不動産資料や預貯金・有価証券等の残高証明書を金融機関から取り寄せていただき、生命保険やその他財産に関わる資料を集めていただく段階でおよそ3~4ヶ月かかってしまう事例が多いです。
中には相続発生日から半年以上過ぎてから届く通知もあります。
それらの資料をもとに土地評価や預貯金の過去5年分の入出金調査を進めていき財産の総額を確定していきます。その後確定した財産資料をもとに相続人全員による遺産分割協議を行い遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書が作成されてようやく相続税申告が可能になりますので、どうしても、長期になってしまいます。